宅建の勉強して、めちゃくちゃ怖い制度を知った。
配偶者短期居住権。
名前だけ見ると「良い制度っぽい」んですけど、実は落とし穴がある。
父親が亡くなって、母親が実家に住み続けられる期間って、実は最短で6ヶ月しかないらしい。
「え、配偶者なのに?」って思いません?
今日はこの制度について、分かったことをまとめてみます。
配偶者短期居住権って何?
2020年に新しくできた制度で、簡単に言うと:
亡くなった人の配偶者が、とりあえず一定期間は住み続けられる権利
相続が揉めてても、遺産分割協議が長引いてても、配偶者は当面の間、家を追い出されない。
一見、良い制度に見えるんですよね。
でも、問題は「期間が短すぎる」ってこと。
住める期間、実は6ヶ月だけ
配偶者短期居住権の期間は、2パターンある。
【パターン1】遺産分割が終わるまで 遺産分割協議が終わるまでは住み続けられる。 ただし、最低でも6ヶ月は保証される。
【パターン2】遺言で家をもらえない場合 最短6ヶ月で追い出される可能性がある。
教材で読んだとき、「6ヶ月って短すぎない?」って思った。
父親が亡くなって、葬式やって、遺産の整理して、相続税の申告準備して…
気づいたら半年経ってる。
なんで6ヶ月なの?
これ、配偶者を守る制度のはずなのに、なんでこんなに短いのか。
調べてみたら、理由が分かった。
配偶者短期居住権は、あくまで「一時的な保護」
ちゃんと長く住みたいなら、「配偶者居住権」っていう別の権利を使う必要がある。
でも、配偶者居住権は自動的にもらえるわけじゃない。
遺産分割協議で決めるか、遺言で書いてもらうか、どっちかが必要。
つまり、何も対策してないと、最短6ヶ月で家を出ないといけない可能性がある。
どんなケースでヤバいか
こういう状況だと、マジで危ない:
父親が遺言を残してない。 家を長男が相続することになった。 長男が「早く家を売りたい」って言い出す。 母親は配偶者短期居住権しかない。 6ヶ月後、家を出ないといけなくなる。
「配偶者なのに追い出されるの?」って思うじゃないですか。
でも、法律上はそうなる可能性がある。
実際にどれくらい起きてるの?
相続トラブルのニュース、最近めっちゃ増えてますよね。
特に多いのが、「配偶者が住む場所を失う」系のやつ。
こういうケース、決して珍しくないらしい。
遺産分割で揉めて、家を売ることになって、母親が住む場所を探さないといけなくなる。
70代、80代で引っ越しって、めちゃくちゃ大変。
配偶者居住権との違い
ここがマジで重要。
項目配偶者短期居住権配偶者居住権期間最短6ヶ月終身 or 決めた期間手続き自動的に発生遺言 or 遺産分割協議で決める目的一時的な保護長期的な居住
配偶者短期居住権は、「とりあえず6ヶ月は大丈夫だよ」っていう応急処置。
配偶者居住権は、「ちゃんと長く住める」っていう本格的な保護。
ここを間違えると、マジで詰む。
どうすれば防げるか
じゃあ、どうすればいいのか。
【対策1】配偶者居住権を遺言に書いてもらう 父親に、「家は配偶者居住権として残す」って遺言に書いてもらう。 これが一番確実。
【対策2】遺産分割協議で配偶者居住権を設定 遺言がなくても、遺産分割協議で決められる。 ただし、他の相続人が反対したら無理。
【対策3】配偶者が家を相続する シンプルに、配偶者が家を相続すればいい。 ただし、他の遺産が減るので、バランスが大事。
どれも、生前に話し合っておくことが超重要。
父親が元気なうちに、ちゃんと話しておく。
これがないと、いざというとき詰む。
街で見かける「あの家」も…
最近、地元で空き家が増えてる気がする。
「誰も住んでないのに、売りにも出てない」みたいな家。
もしかしたら、こういう相続トラブルが原因かもしれない。
配偶者が家を出て、でも売れなくて、放置されてる。
こういうケース、実際に多いらしい。
知っておくべきポイント
配偶者短期居住権、名前は優しいけど、実は厳しい制度。
6ヶ月しか保護してくれない。
ちゃんと長く住みたいなら、配偶者居住権を設定する必要がある。
でも、それには生前の対策が必須。
「とりあえず相続が起きてから考えよう」だと、間に合わない可能性がある。
実家に住んでる母親がいる人、マジで今のうちに確認しておいた方がいいかも。
6ヶ月って、思ってるよりあっという間ですよ。
※この記事は宅建学習を通して学んだ内容をまとめたものです。間違いがあればご指摘ください。
▼ 配偶者居住権についてもっと知る
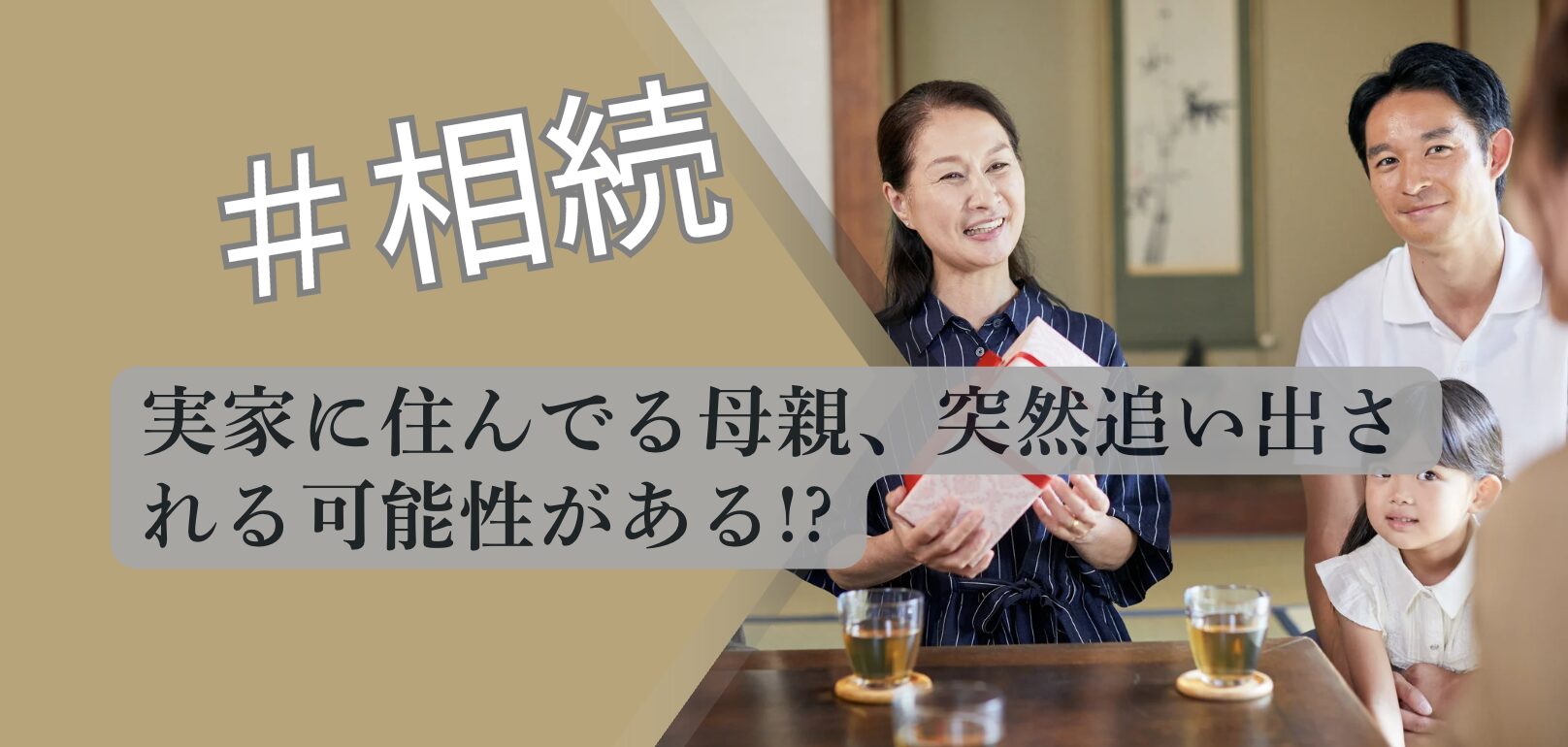


コメント